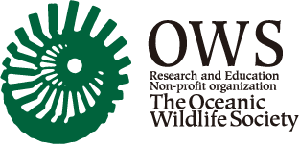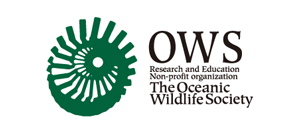調査対象の造礁サンゴとは?

海岸に打上られたサンゴの骨格標本
造礁サンゴとは
造礁サンゴとは、石灰質の骨格をもち褐虫藻を共生させて、その光合成による養分補給を受けるため成長が速く、サンゴ礁の基礎をなすサンゴの種称です。
同じ石灰質の骨格をもつが、褐虫藻を共生させない非造礁サンゴとは区別されています。
調査の対象は、この造礁サンゴです。
分布は琉球列島に代表されますが、海流の影響により、太平洋沿岸では、伊豆半島、三浦半島を経て、千葉県の房総半島、東京湾まで分布し、日本海沿岸では、壱岐・対馬、隠岐、能登半島、佐渡を経て、山形県鶴岡市の沿岸にまで達しています。
それら分布北限域に生息している造礁サンゴの仲間は、おおよそ40種類前後。高緯度地域には低水温に耐性をもつ限られた種が生息しています。
これらの地域では一部に樹枝状のサンゴ群落が見られるものの、いわゆるサンゴ礁地形が形成されることはなく、多くが被覆状、塊状の群体がまばらに点在する場合が多く、色彩的にも比較的地味であるため、同様の外観を持つ、石灰藻やカイメンなどの仲間と見分けにくいので、慎重に観察する必要があります。